台湾を歩くと、季節ごとに街が色で語り出すことに気づきます。春節には視界が赤に染まり、端午の頃には緑が町の輪郭をやわらかく包みこみます。
最初は「華やかな飾り」だと思っていた色が、実は深い祈りのサインだと知ったのは、現地での小さな失敗と会話がきっかけでした。私は友人のマリエさんと台湾を巡り、春節の夜市と端午の川辺を体験しました。
現地の声、匂い、そしてスマホに残した一枚一枚の写真。色とともに刻まれた記憶は、観光以上の学びをもたらしてくれました。今回は、私たちが「誤解し、気づき、理解した」体験を軸に、「赤」と「緑」が今も息づく理由と背景を辿ります。

春節の「赤」|祝祭ではなく、家族を守る「結界」の色
台北の春節初日。赤い提灯を見て「お祝いムードだね」とつぶやいた私でしたが、夜市の写真を見返すうちに印象が変わりました。春聯や紅包、赤い紙が街に整然と並び、まるでひとつの儀式のようだったのです。
宿の主人はこう語ります。
「赤は家を守る炎の色。これがないと年は始まらない」
その言葉で、赤を飾りだと思っていた自分に気づきました。台湾の赤は、祝祭のための華やかさというよりも、年の始まりを整え、家族の安心を包むための色だったのです。
赤に染まる迪化街|年貨大街で感じた「福」を分け合う力
特に台北の迪化街(ディーホアジエ)で開催される「年貨大街(正月用品市場)」は、街全体が赤いインクをこぼしたような熱気に包まれていました。
軒を連ねるカラスミの鮮やかな朱色、無数に吊るされた赤い提灯、そして山積みにされた紅包(お年玉袋)。人混みの中でカラスミを試食させてもらったとき、店主が「赤い色は太陽の恵み。たくさん食べて福を連れて帰りなさい」と笑ってくれました。
マリエさんと「歩くだけで元気がもらえるね」と話しながら、ただの買い物ではなく、赤という色を通じて街全体で「福」を分け合っているような、圧倒的なパワーを肌で感じました。

夜市で見つけた、安心を包む「紅包」の重み
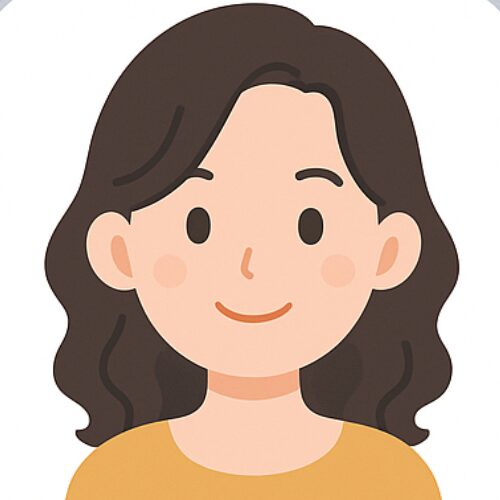
私たちは夜市で、紅包を渡す場面を写真に収めました。ただの“お年玉”ではなく、「幸運を次へ運ぶ儀式」だと知ってから、その一瞬の重みが伝わってきました。
- 春聯(しゅんれん)=家を守るための結界のような存在
- 紅包(ほんぱお)=祝福を“渡す行為”そのもの
- 街の赤=共同体が同じ願いを共有する合図
端午の「緑」|病を遠ざけ、健やかな暮らしを願う「知恵」の色
梅雨入り前後、台中の市場は緑に包まれていました。竹葉に包まれた粽が山のように積まれ、束ねられた香草が風に揺れ、空気には青く澄んだ香りが混ざります。
店の女性が私の視線に気づいて、「この草を吊るすと、病が寄らないのよ」と微笑みながら教えてくれました。そっと小さな束を手に取らせてもらうと、掌にひんやりとした感触が残りました。まるで“自然の守り”を分けてもらったようでした。

市場の香草と竹葉に宿る、自然の守り

端午の緑は、ただ美しいだけではありませんでした。香草を束ね、竹で包み、自然の力を暮らしに取り込む。そこには、健康と無事を願う静かな祈りが息づいていました。
緑をほどいて味わう|粽に包まれた健康への願い
その後、市場で買った粽(ちまき)を包みから解くとき、マリエさんが「この紐をほどく瞬間が、お守りを開けるみたい」と言いました。
竹の葉の深い緑色から現れる、つやつやとしたもち米。一口食べると、醤油の香ばしさとともに、竹の葉の清々しい香りがふわりと鼻を抜けていきます。
店のおばあちゃんが「具材の栗や豚肉は、どれも家族の健康を願う意味があるんだよ。この葉っぱがその願いを逃さないように包んでいるんだ」と教えてくれました。
この「緑の包み」が、いかに大切に受け継がれてきた愛のある知恵なのかを、五感すべてで噛み締めた瞬間でした。
- 香草を吊るす 疫病を遠ざける、暮らしの知恵。
- 竹葉で包む粽 自然の力で“包み、守る”という行為。

現代にも続く“緑の意思表示”
今でも端午の時期になると、緑を基調としたパッケージや限定商品が並びます。それは流行ではなく、「健康でありたい」「自然と共に生きたい」という想いの延長線に見えました。
- 香草を吊るす=疫病避けの暮らしの知恵
- 竹葉の粽=“包む”という行為に宿る守り
- 街の緑=自然と調和する意思のしるし
【実用ガイド】台湾の色彩をより深く体感するために
色の意味を知ってから旅をすると、同じ景色でも“見え方”が変わります。ここでは旅行者が迷いやすい「いつ」「どこに行けば体験できるか」を、わかりやすく整理しました。
| テーマ | 時期(目安) | おすすめの場所 |
|---|---|---|
| 赤(春節) | 1月下旬〜2月(旧正月前後) | 台北・迪化街「年貨大街」/夜市周辺 |
| 緑(端午) | 5月下旬〜6月(旧暦5月5日前後) | 各地の市場/河川敷(ドラゴンボート会場) |
色彩を楽しむ旅のQ&A(旅行者の迷いどころ)
色の意味がわかってくると、次に迷うのは「旅行者としてどう振る舞えばいい?」という小さな実践です。私たちも現地で戸惑ったポイントを、安心して楽しむための目安としてQ&Aにまとめました。
- Q:春節に赤い服を着ていくべき? A:全身赤でなくても大丈夫です。バッグや小物など、ワンポイントで取り入れると「一緒にお正月を楽しんでいるね」と笑顔を向けてもらえることがあります。
- Q:端午の粽(ちまき)はどこで買える? A:市場・専門店・デパ地下・スーパーで見つかります。端午の時期は竹葉の香りが濃く、季節ならではの空気ごと味わえます。
- Q:色の意味をもっと知りたいときは? A:「この色にはどんな意味があるの?」と一言聞くだけで、暮らしの背景ごと教えてくれることが多いです。
まとめ|色は「見るもの」ではなく「感じる文化」
春節の赤は、家族と繁栄を願い、年の始まりを整える「守りの色」。端午の緑は、自然の力を暮らしに取り込み、健康を願う「知恵の色」。台湾の街を歩くと、そのどちらもが人々の生活の中で息づき、言葉よりも雄弁に想いを伝えていました。
旅のはじめ、私は色を「きれいな背景」だと思っていました。けれど、光や香り、人の声とともに刻まれた記憶は、写真よりも鮮やかに心に残ります。
赤と緑の背景にある物語に目を向けると、旅はただの観光を超え、人と文化のぬくもりに触れる体験へと変わります。次の台湾旅では、軒先の飾りや市場の匂いに宿る「色のメッセージ」に、そっと耳を澄ませてみてください。
こちらの記事も参考にどうぞ!
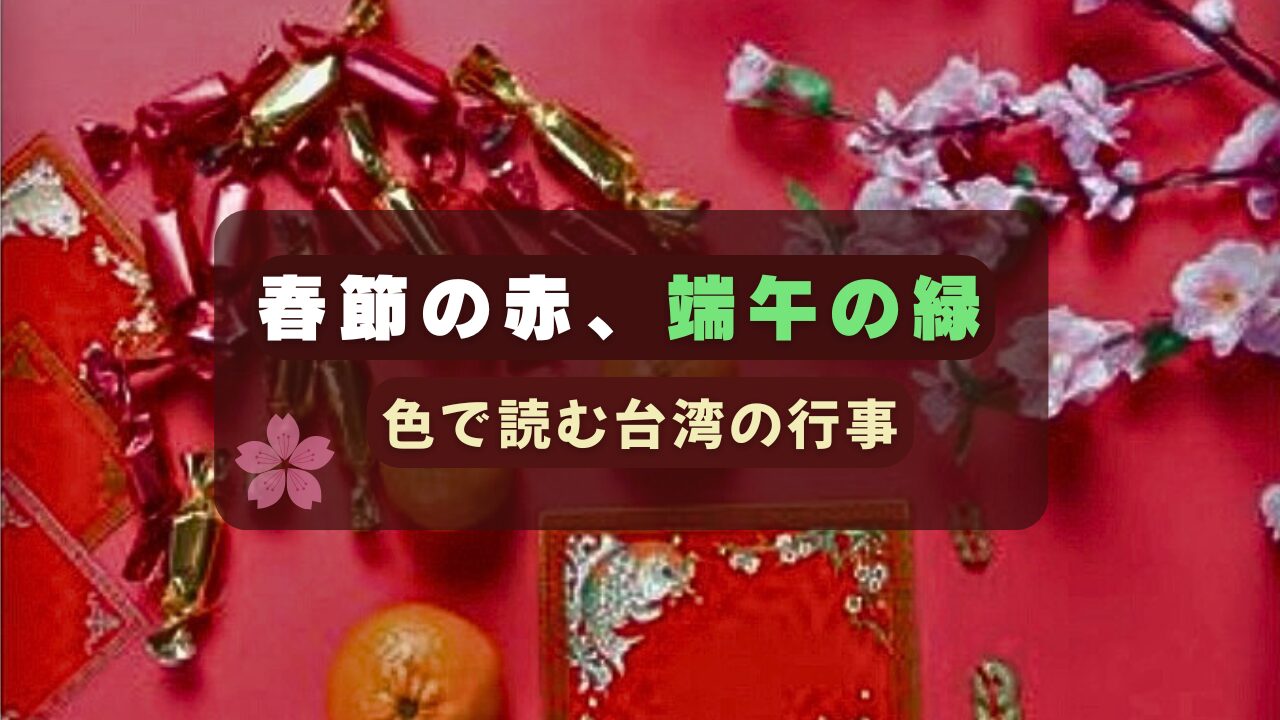


コメント